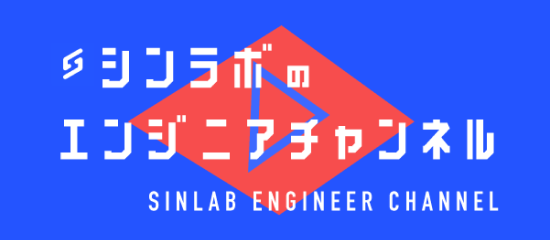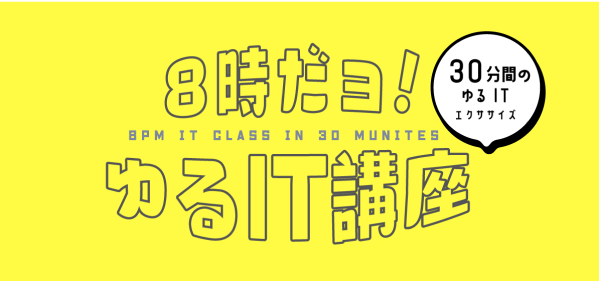ふぁみカル君開発 (2020/04)リーダーの頭の中はというと…

ふぁみカル君、プロジェクトリーダーの緒方です
唐突ですが、集まってくれている開発メンバーには、いつも感謝しかありません
色んな人に、こう聞かれるんです
「その人達ってさー、何でコレナオ(私の事です)のやつ開発してくれてんの?」
構想に共感してくれているから? 自分のスキル向上のため? 単なる暇つぶし?(んなわけないw)
私はものを作れる人間では無いので、チームの中に居ると、自分がすべき事は何だろうと、つくづく考える事になります
事業の方向性は? 本当に解決すべき課題は? 全体の流れは? 利益とは?
リーダーと呼ばれる人ってこういう事を考えるのかなぁと、これはこれで勉強になります
さて、「事業の方向性」という観点で、最近の自分の活動を書いてみたいと思います
先日、個人的な繋がりで「ミルフィーユ小児がんフロンティアーズ」の代表と会っていました
①小児がん患者とその家族 ②治療に関係する医療機関や団体すべて
この2つの間に立って、様々な活躍をされている人(組織)です
そもそも「ふぁみカル君」は、診療を管理して、家族で共有するという、新しい医療の形を実現するものです
開発中のアプリを見ると、普段皆さんが病院やクリニックに行く時にしか使わない印象ですが、将来的には、「がん」の様な、長い間付き合っていく病気にも対応できるようにします
その為にも、今回の対談はとても有意義でした
※下の写真は、頂いた会報誌
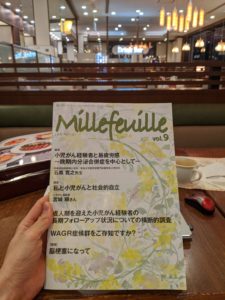
対談では主に2つのことを話しました!
①自分の病気や診察の結果をしっかりと把握すること
・米国を例に挙げると、基本的に病院が少ないので、患者は自宅で療養や治療を行う
だから、必然的に「医療はサービス」と捉えていて、患者は「主体的・能動的」に動いている
・日本人のリテラシーや関心が高くない理由は、保険制度や文化が原因だと思うけど、まぁこれは言っていても仕方ない
②がんも対象にすべき
・日本人の2人に1人が関係があるし、自宅でのフォロー(経過)が社会生活と大きく関係する
ふぁみカル君は、自宅でのフォローを手助けしてくれるサービスになる
多くの人が使ってくれれば、色々な援助(人材、情報、機会、資金など)を受けやすい
・がんは高齢者が多いので、ふぁみカル君を使うのは、家族の中間である私たち「30代~50代」になる
・高齢者に限らず、小さいころに患って大人になった「AYA(あや)世代」も対象になる
取りあえず、今回は以上~
ライター: 緒方 これなお
担当:ふぁみカル君の発起人、開発はできないのでそれ以外のジャンル
現職とのバランスに苦戦しつつも、メンバーに支えられながら「ふぁみカル」が普及した世界を妄想中。
https://peraichi.com/landing_pages/view/famikar
EVENTS